軽症者の中継地点経由の搬送による救急車利用の緩和策
経営戦略の動画を見ておりましたら「移動時間の短縮が生産性向上になり、そのためには特定地域のお客様を多く作っていくと良い」ということを聞きました。
ランチェスター経営株式会社 竹田陽一先生が、下記動画の10分45分のところで「移動時間が生産性を下げる大きな要因になっている」そのため、「特定地域の中にお客様を多く作っていく」と述べられております。
【スペシャル対談】アフターコロナに向けて取り組む 最も大切なことは何か!竹田陽一先生×佐藤元相
この「移動時間を短縮する」という面において、重症病床の逼迫の回避に応用できないかと、素人ながら考えてみました。
コロナ患者の自宅と病院との間に中継地点(広い体育館等の暫定施設 ※但し災害時も考慮要)を設け、中継地点から病院間を救急車ではなく、中型トラックを蔓延防止措置の救急用に改良した車両で搬送します。
重症化の患者は救急車で緊急搬送しますが、軽症者は暫定施設で治療を受けて頂き、中症者は、改良済み中型トラックで病院へ搬送します。
病院側では1度の人数分の受入れ体制を整える必要はございますが、搬送効率が上がると同時に軽症者の病院へ人数を抑制し、病床逼迫の回避に効果的だと考えております。
- 重症者:救急車で病院へ緊急搬送
- 中症者:改良済み中型トラックで病院へ搬送
- 軽症者:中継地点(暫定施設)で治療
中型トラックの改良点(救急用:蔓延防止措置)
- 荷台部分に患者を乗せ、落下しないようドーム型(屋根付)の柵を取付けます。
- 柵は、通気性の確保のため網目状にし、また、雨天時に雨水を受けても車両外側で流れ落ちるように設計し、カーボン製等で白や水色等に塗装します。
- 網目状の通気口の大きさや角度は、走行時、通気口からの空気が全て後ろ側に流れ出てドーム内が換気されるように設計します。
- ドーム頂上にサイレン装置を設置し、救急の走行を可能にします。
- 運転手以外に救急隊員1名はドーム側に乗車し、患者へ携帯酸素缶を配布し、酸素不足時は、医療用酸素ボンベから携帯酸素缶への酸素吸入を支援します。
<ご参考>
- 携帯酸素缶 携帯型酸素吸入器 スポーツ酸素DXセット
※マスクの下から滑り込ませて使用可?
空き重症病床早期確保のためのLINEグループの活用
コロナ患者が退院や別の病院へ移る場合は、相手側の受入れ体制やその他の様々な要因によっても変わってくるため、患者お一人お一人に対するきめ細やかな対応が必要になってくるとお聞きしたが事が、あるニュース番組(NEWS23?)で関東圏のコロナ患者の退所を管理するシステムについてどなたかがお話をされていた時に聞いたことがございます。
どの病院についても、医療従事者の負担を軽減し、きめ細やかな対応ができれば、軽症へと向かう重症者の退所を早めることができ、病症確保が早まるのではと思いました。
患者への「きめ細やかな対応」にあたっては、病院が運営するLINEグループに、患者のご家族の方に入って頂くことが可能になれば、情報のやり取りが行われやすくなり、退所条件クリアのための行動が促進されていくものと思われます。
ご家族の方々にLINEグループに入って頂くためには、病院側システムで入力された患者の病症データ(毎日の体温、血圧などの健康情報、担当医師のコメント等)を、LINEグループを活用してご家族の方に自動配信できれば、ご家族の方々は安心感が得られメリットとなるため、ご協力が得られやすくなるのではと考えております。
病院側としては、医療従事者はコロナ患者の治療に専念するのが望ましく、また退所の効率があがることで回転率が向上し、本来の果たす役割や治療人数が多くなるため、上記の退所の手続き的な部分については投資対効果で考えてアウトソーシングし、下記点などをふまえた退所手続きが行える業者が良いのではと考えております。
退所手続に特化した委託業者
- LINEグループの開設
- 退所条件クリアのための、LINEメッセージでのご家族とのやり取り
- 退所条件クリアのための、入退所に関わる他病院との情報共有システム
- 病症データ自動配信のための病院側システムとLINEグループの接続設定
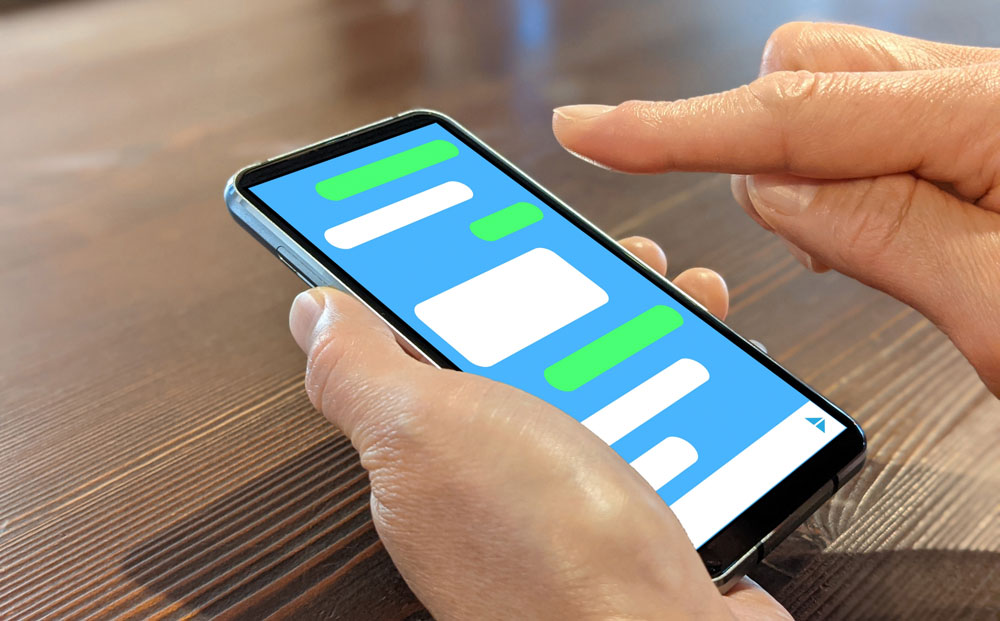


コメント